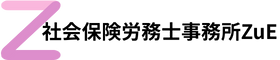【社員の定着に活用!】介護離職を防ぐ3つの対策
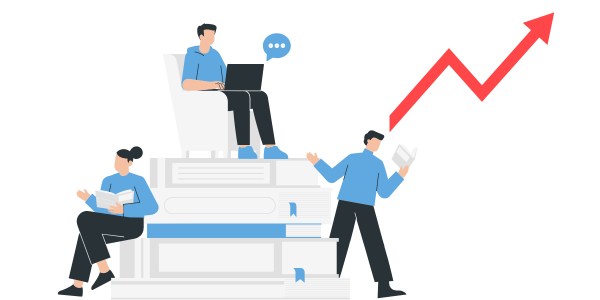
こんにちは、こくぶんです。
「社員が、家族を介護することになっても働き続けてもらうには、どうしたらいい?」と悩んでいませんか?
今回の記事は、介護離職を防ぐための3つの対策をご紹介します。
.png)
対策①:社内の制度を整備する
介護に関する社内制度を整備しましょう。
対象家族を介護する社員が生じた場合に備え、どのように対応するかを決めておき、規定に定めておきましょう。
介護休業に関する定めは、育児・介護休業法にあります。
企業の義務として、介護休業のほか、下記に関する内容が定められています。
・介護休業制度
・介護休暇制度
・所定労働時間の制限
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・介護に直面した旨の申出があった場合における措置等(※)
・介護に直面する前の早期の情報提供(※)
・介護休業、介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備の措置(※)
・介護のための所定労働時間の短縮等の措置
・労働者の配置に関する配慮
・不利益取扱の禁止
法律で定められていることを、下回ることはできません。
また、(※)印の項目は、令和7年4月1日から新たに施行された部分です。
社内届出用の様式や、必要に応じて労使協定も備えましょう。
働き続けてもらうには、「制度を利用してもいい。」という社内の雰囲気をつくっておくことも重要です。
制度の整備にあわせ、企業方針も明確にしておくとよいでしょう。
.png)
対策②:個別周知と意向確認
「個別周知と意向確認」は、法律で定められていることではありますが、実務において重要です。
社員が介護をしていることがわかったら、個別周知と意向確認を必ず行いましょう。
ここでいう個別周知とは、「介護に関する制度等について、個別に知らせること」です。
また、意向確認とは、「制度を利用するかどうかの意向の確認」を指します。
個別周知の内容として、法で定められている内容は、次の通りになります。
・介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等
・介護休業および介護両立支援制度等の申出先
・介護休業給付金に関すること
介護両立支援制度等とは、「介護休暇に関する制度、所定外・時間外労働の制限に関する制度、深夜業に関する制度、所定労働時間の短縮等の措置」です。
介護休業は「要介護状態にある対象家族の介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するもの」として位置づけられています。
介護は育児と異なり、いつまで介護するのか、予測することは難しいでしょう。
介護休業は法定上、対象家族1人につき、93日を限度に、3回まで分割可能です。
個別周知の際には、社員が介護休業取得後も働き続けられるよう、「介護の体制を構築する」という介護休業の趣旨を伝えましょう。
個別周知・意向確認の方法は、面談又は書面の交付が原則ですが、社員が希望する場合は、FAXも可能です。
また、社員が希望する場合、かつ、記録を出力することにより書面を作成できる場合は、電子メール等でもよいです。
記録も残しておくとよいでしょう。
.png)
対策③:業務の棚おろし・共有
介護は、突然必要になる場合があります。
法定上、介護休業の申出期限は、「介護休業を開始しようとする日の2週間前まで」となっていますが、業務を引継ぐための十分な時間が取れない場合があるでしょう。
突然の休業でも業務フォローできるよう、あらかじめ業務の棚おろしを行い、共有しておくことをお勧めします。
業務の棚卸の方法としては、部署ごとや職種ごと、もしくは社員ごとの業務を書き出し、一覧などにして、「見える化」することが考えられます。
社員それぞれが担っている業務とその進捗を、把握できる体制を整えることで、共有することができます。
.png)
【まとめ】
家族の介護は、多くの方にとって可能性があります。
介護休業などは法に定められた企業の義務ですが、職場の雰囲気づくりなども行って、社員の定着に活かしたいですね。
介護休業は、社会保険料免除がありません。
休業中の社会保険料を、どのように納めてもらうかについても、あらかじめ定めておくとよいでしょう。
介護に関する社内制度の整備や運用など、社会保険労務士事務所ZuEはサポートしています。
ぜひ、お問い合わせフォームもしくはお電話から、お問い合わせください。