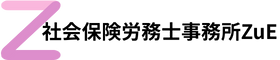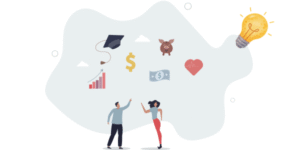【4つの疑問で解決!】「介護休業」とは。

こんにちは、こくぶんです。
「社員から、介護休業を取りたいと言われたが、介護休業ってどういう場合に該当するの?」と悩んでいませんか?
今回の記事は、育児・介護休業法で定める「介護休業」を、次の4つの疑問に沿って説明します。
.png)
疑問①:「介護休業」とは?
介護休業は、「労働者(以下、社員という)が、要介護状態にある対象家族を、介護するためにする休業」です。
言葉の意味を説明します。
「要介護状態」:「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態」を指します。
例えば、対象家族が、風邪などで3日間の介護を必要とする、という場合には「2週間以上」に該当しないため、介護休業の「要介護状態」にはなりません。
介護休業の要件である「要介護状態」は、介護保険の要介護状態とは必ずしも一致しないため、休業を希望する社員から話を聞き、判断することになります。
「要介護状態」の判断にあたっては、「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が示されており、令和6年(2024年)の改正で、見直しが行われました。
「対象家族」:「配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫」です。
配偶者には、事実婚も含みます。
「介護する」:「歩行、排泄、食事、見守り等の日常生活に必要な便宜を供与すること」を指します。
社員が、日常生活に必要な便宜を供与していない場合は、利用できません。
.png)
疑問②:取得できる社員は?
日々雇用される方は取得できません。
契約社員など、期間を定めて雇用される社員は、申出時点において、介護休業の取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過するまでの間に、労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合は、取得できます。
また、労使協定で定められた社員は、取得できません。
労使協定で定めることができる社員は、次の3つに限られます。
・継続して雇用された期間が1年に満たない方
・申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな方
・1週間の所定労働日数が2日以下の方。
.png)
疑問③:どのくらいの期間、取得できる?
介護休業を取得できる期間は、対象家族1人につき、93日までを限度に、分割3回までです。
取得日数と取得回数に制限があり、どちらかが上限に達すると、もう一方が残っていても、取得できません。
例えば、実母の介護のため、1回目30日、2回目15日、3回目15日、合計3回の介護休業を取得した場合、取得回数が上限に達していますので、取得日数は93日に達していませんが、取得できません。
.png)
疑問④:取得手続きに決まりがある?
取得手続きに、決まりがあります。
法律の介護休業は、社員からの申出を要件としています。
介護休業の申出は、原則、書面により行わなければなりませんが、企業が認める場合には、FAXでも可能です。
企業が認め、かつ記録を出力し書面を作成できる場合は、電子メール等でもよいです。
申出を受けた場合、次の内容を社員に通知しなければなりません。
・介護休業の申出を受けたこと
・介護休業の開始予定日と終了予定日
・介護休業の申出を拒む場合は、拒む旨と拒む理由
介護休業の申出は、開始予定日の2週間前までに行われた場合、予定通り取得させます。
開始予定日の2週間前までに行われなかった場合は、申出から2週間までの間で指定することができます。
.png)
【まとめ】
法律の介護休業の定めを、下回ることはできません。
また、介護休業と介護休業給付金の要件は異なるため、介護休業に該当し、法律通り取得したとしても、介護休業給付金が支給されない可能性があります。
制度をきちんと説明し、社員には、納得・安心してもらいたいですね。
介護休業に関する手続きやご不明点に関する相談など、社会保険労務士事務所ZuEはサポートしています。
ぜひ、お問い合わせください。